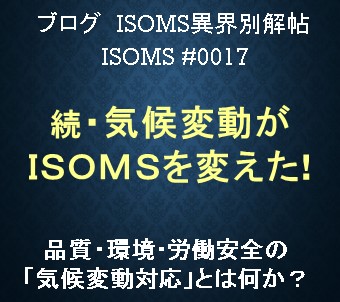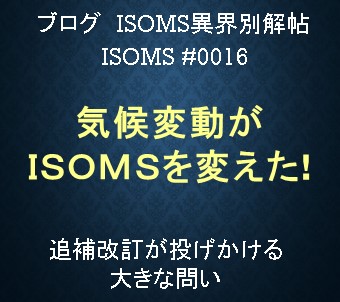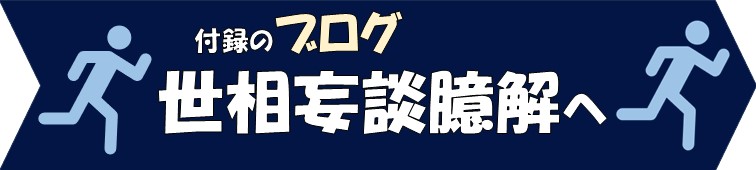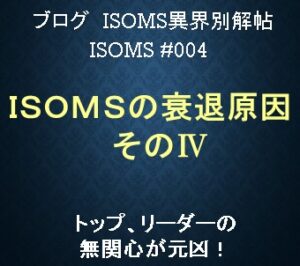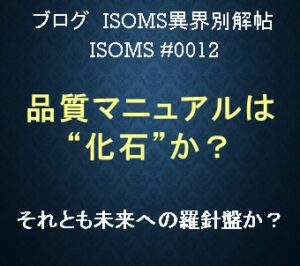続続・気候変動がISOMSを変えた!
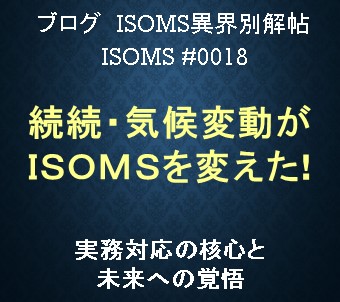
実務対応の核心と、未来への覚悟 ISOMS#018
ISOMSへの気候変動追補に関するブログの3回目です。
近年、世界中で起きる異常な自然災害の源と考えられる気候変動に対して、ISOMSに取り組む私たちに何ができるか、考えましょう。
目 次
はじめに
2024年2月の追補は、ISOMSでは「小改訂」の規模でしたが、その中に含まれた「気候変動」という言葉は、企業に大きな「問い」を投げかけ、社会に「決断」を促すものでした。
それは、品質でも、環境でも、安全衛生でも、“気候変動抜き”では語れない時代に入ったという宣言でもあります。
したがって私たちは、
- 単にマニュアルを書き換えるのではなく、
- 単に審査員に解釈や方向性をまかせるのでもなく、
“地球規模の課題を、自社の課題として腹に落とす”
その覚悟こそが問われています。
1. 我々組織は、どう対応すべきか?
2024年2月の追補により、ISOMSの4.1項・4.2項には「気候変動」という新たな視点が公式に組み込まれました。
しかし、「条文を追記した」「マニュアルを修正した」で終わらせてはなりません。
この追補は、単なる文言ではなく“問い”そのものであり、具体的な行動喚起なのです。
- 問1:「我が社は、気候変動の加害者なのか? 被害者なのか?」
- 問2:「我が社にとって、気候変動は“関連課題”なのか?」
- 問3:「我が社の利害関係者の期待や要求は、気候変動にどう結びつくのか?」
この3つの問いに答える過程こそが、追補対応の本質です。
まず、全社員で「気候変動とは何か?」、「その何に影響され始めたか?」、さらに「何に我社の活動、製品が影響を及ぼしているか?」を、自分たちの言葉で再定義し、事例を洗い出して現場に根ざした共通認識と危機意識を築くこと。
ここに立脚してこそ、「組織の状況」と「利害関係者の期待」の真の解釈が見えてくるのです。
そのためには、以下の行動が求められます:
▷ 実務5ステップ
① 現状把握と棚卸し
- 自社の業務が、どのように気候変動に関与しているか(原因系)
- 気候変動によって、どのような影響を受けるのか(結果系)
② マネジメント方針の修正
- 品質・環境・労働安全それぞれの基本方針に「気候変動」対応を明記
③ 関連文書の再整備
- 4.1/4.2だけでなく、5.1(リーダーシップ)や6.1(リスクと機会)にもリンクを張る
- それらをネットワーク構造として関連文書の整合性を持たせる
④ 教育・訓練の実施
- 気候変動に関する知識を社員全体で共有
- 現場の実務に落とし込む「翻訳」が不可欠
⑤ 継続的改善と見直し(PDCA)
- 気候変動の状況は常に変化する。定期的なレビューでPDCAを回す文化を醸成
2. 審査機関はどう対応するのか?
審査機関もまた、この追補に対して「態度」を示しています。
日本の審査機関を統括するJAB(日本適合性認定協会)は、2024年4月2日付で各審査機関に通知を出し、「気候変動に関する評価視点の導入」を指示しました。
これを受けて、多くの審査員たちが、以下の観点で審査対応を始めています。
▷ 審査上の重点4項目
① 気候変動のリスクと機会が、適切に特定されているか?
- 事業継続リスク、納期遅延、温暖化対策等に対応が組み込まれているか
② 具体的な行動計画が存在するか?
- 温室効果ガス削減、酷暑対策、異常気象BCPなどが明文化されているか
③ 教育・訓練が実施されているか?
- 気候変動リスクへの備えについて、現場従業員に理解が浸透しているか
④ 規格間の整合が取れているか?
- ISO9001/14001/45001の各規格で、気候変動への方針や施策に一貫性があるか
ただし、現段階でこれらが不適合として厳しく指摘されるケースはほとんどなく、審査員の多くは「現状の確認」と「適切なアドバイス」にとどめており、過剰な是正要求を控える傾向にあります。
とはいえ、将来的にはこれが「当然の審査項目」として定着するのは明らか。
今のうちに備え、実行しておくことが組織の信頼性を高める最良の道となるでしょう。
3. まとめ:次代へ渡す「未来に向けた使命」
この追補の次に来るのは、2026年以降に予定されている本格的なISO 9001・14001の改訂です。
そこでは「気候変動」だけでなく、「デジタル化」「人権」「サーキュラーエコノミー」など、多様な新要素が織り込まれることが予想されています。

だからこそ今、気候変動をめぐるこの“最初の一歩”を、形式で終わらせず、血肉化することが問われているのです。
この小さな追補から学び、未来の世代に渡すべき「地球と経営の両立モデル」を築いていくこと――
それが、いま私たちの手に託された“組織の責任”であり“希望の種”なのです。