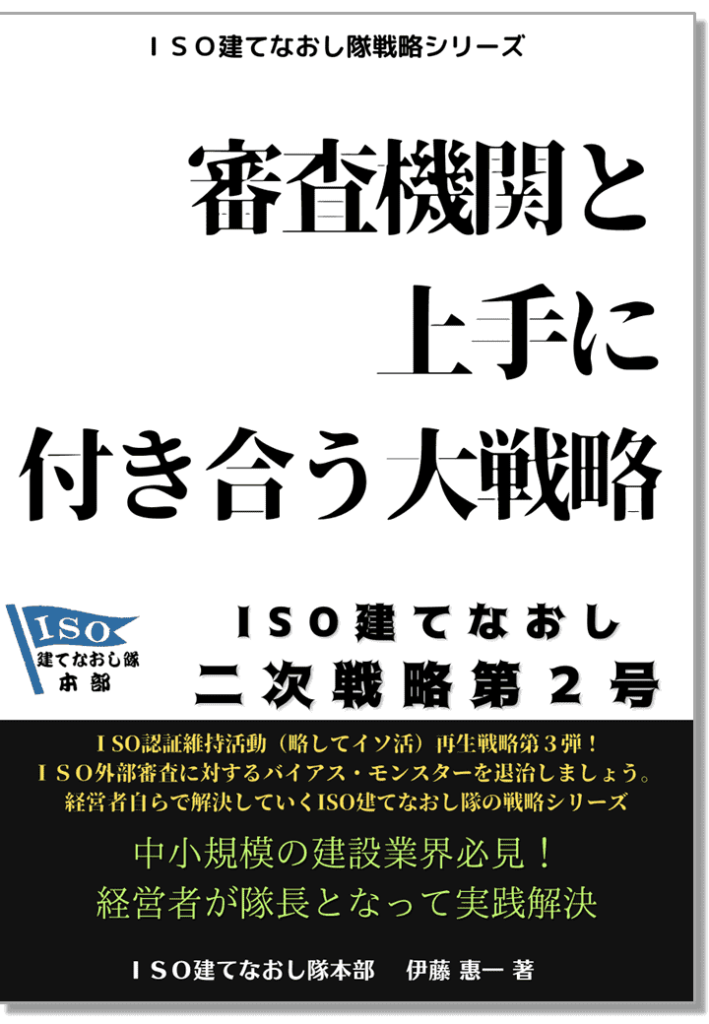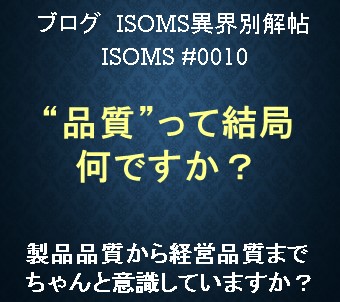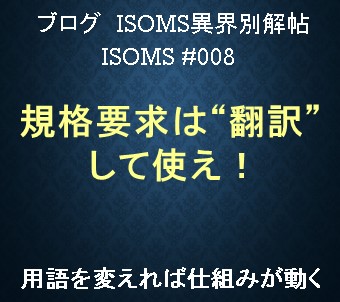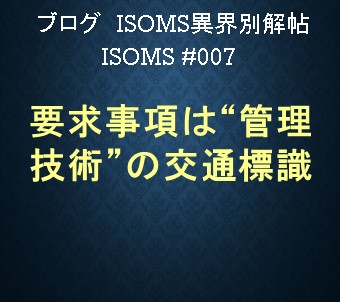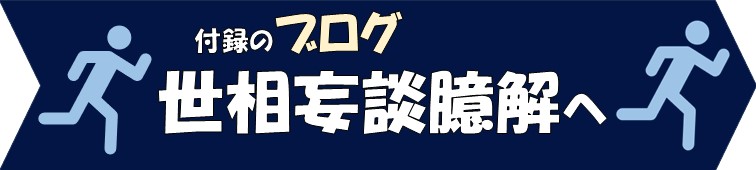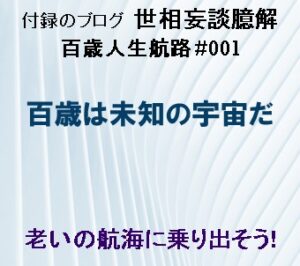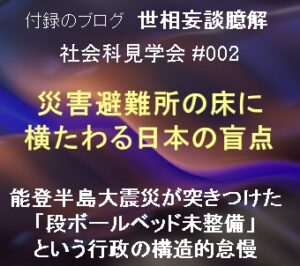外部審査員は神様じゃない!
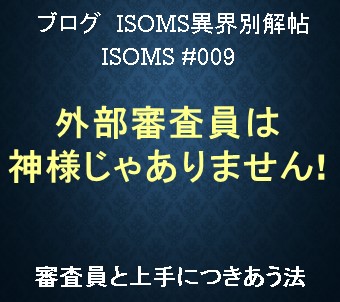
審査員と上手につきあう法 ISOMS #009
本ブログでは、ISOMS受審組織の方々が一応にビビる
外部審査機関の審査員との付き合い方について解説します。
目 次
はじめに:審査は“判決”ではなく“対話”です
ISOMSや他のマネジメントシステム(MS)の認証を取得している組織にとって、外部審査は避けて通れないイベントです。
しかし、現場では「審査員に怒られるのでは?」
「粗探しされるのでは?」といった不安の声が絶えません。
そのため、形式的な準備や“見せる用”の帳票作成に追われ、本来の目的である“仕組みの改善”が
後回しになることも珍しくありません。
外部審査を「怖いもの」「面倒なもの」としてではなく、組織の成長を促す“よき対話の機会”として活用するために、どのような姿勢と準備が必要なのか、ここで考えてみましょう。
1. 審査員もまた“人”である
まず大前提として、審査員は神ではありません。
超越的な目を持つ裁定者ではなく、組織の仕組みを客観的に見て、改善のヒントを探す支援者です。
もちろん、規格要求事項に対する適合・不適合の判定は行いますが、その根底にあるのは「客観的証拠に基づいた評価」というルールに沿った作業です。
審査員も一人の人間であり、過去の現場経験や知識に影響される部分があります。
だからこそ、審査の場では“恐れる”のではなく、“正直に、対話的に”向き合う姿勢が大切です。
うまく説明できない場合でも、現場の工夫や背景を率直に伝えることで、審査員の理解を得られることが多くあります。
2. ”指摘”は叱責では無くフィードバック
審査で「不適合」や「改善の機会」といった指摘を受けると、どうしてもマイナス評価のように感じてしまいがちです。
しかし、これらは決して「ダメ出し」ではなく、組織がよりよくなるためのフィードバックなのです。
たとえば、「この記録の保存根拠が曖昧ですね」という指摘があったとしましょう。
これは「あなたの業務は間違っている」と断罪しているのではなく、「改善の余地がある点」を一緒に見つけ出してくれた結果での言葉です。
つまり、審査で出された指摘は、「問題」ではなく「改善テーマ」として捉えることが重要です。
審査を通じて、自分たちでは気づかなかった視点を得られることは、むしろ貴重なチャンスといえます。
3. “見せるため”から“使うため”の仕組みへ
審査前になると、いまだに「形式的な帳票を整える」、「実態と違う記録を“取り繕う”」といった準備に追われる組織も少なくありません。
しかし、こうした取り組みは見せかけの“演技”に過ぎず、組織の本質的な改善にはつながりません。
本来、マネジメントシステムは「使う」ための仕組みであり、「見せて良い点数を取る」ための道具ではありません。
帳票や記録も、日常業務の中で本当に必要なものを整備し、使いながら改善することが大切です。
日頃全く使わないのに審査前に皆で中味を創作する記録なら、廃止する勇気を持ちましょう。
年一回の審査ならば、普段通りに積み上げた一年分の実態をそのまま見てもらい、「ここを直すともっと良くなりますね」といった建設的な対話につなげていくのが理想です。
但し審査員はコンサルタントではありませんから、具体的な指示はご法度であることを理解しておきましょう。
4. 審査を”内省の機会”として活かす
外部審査は、組織にとって貴重な“内省の時間”です。
日常業務に追われていると、なかなか自分たちの仕組みを見直す余裕がありません。
しかし、審査という場があるからこそ、日頃の取り組みを振り返り、仕組みの強みや課題を言語化することができます。
さらに、審査で得られた視点やフィードバックは、単に規格への適合性を高めるだけでなく、
顧客満足の向上や組織の信頼性向上にもつながります。
審査を“こなすイベント”ではなく、未来を見据えた対話”と位置づけることで、マネジメントシステムは生きた仕組みへと成長していきます。
まとめ
外部審査は、決して「試験」や「査問会」ではありません。
審査員は神様ではなく、対話の相手であり、組織の鏡でもあります。
「何を言われるか」と身構えるのではなく、「何が見えてくるか」に耳を傾けましょう。
その視点で審査を迎えれば、形式的な準備に追われることなく、本来の目的である「仕組みの改善」と「現場の成長」につながるはずです。
審査を恐れず、上手につきあう力こそが、真のマネジメント力なのです。
また審査を怖いものと組織内で印象操作する管理者もいますが、
それ自体がISOMSの形骸化を進めていることに気づかなくてはならないことは言うまでもありません。
《参考図書》
本ブログと関連してオフィス・リベルタスでは、次の図書をKINDLE電子書籍で発行しています。
どうぞ参考にご購読ください。