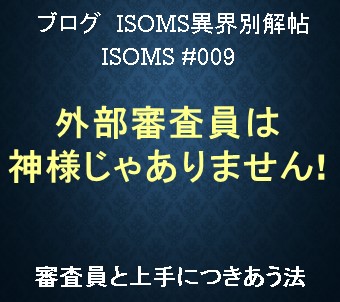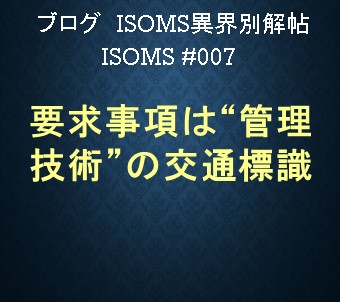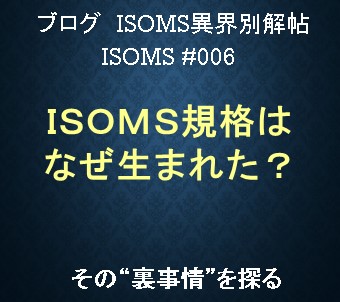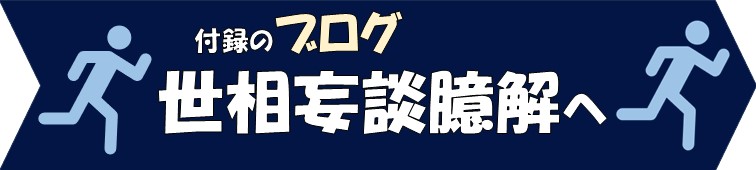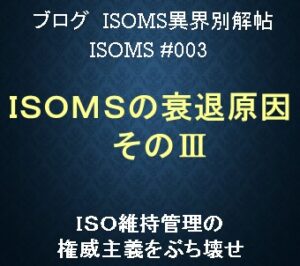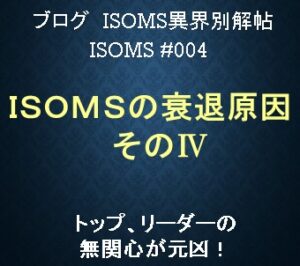規格要求は“翻訳”して使え!
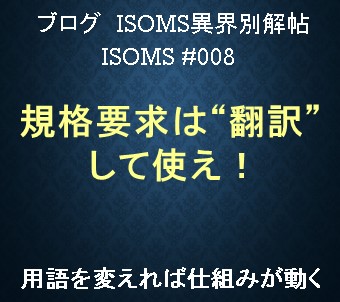
用語を変えれば仕組みが動く ISOMS #008
このブログでは、ISOMS規格の用語使用に囚われずに、従来から用いている組織内の言葉に置き換えるメリットについてお話します。
目 次
はじめに:ルールは”押しつけ”ではなく”味方”に
ISOMS規格の要求事項は、現場にとって「お役所的な縛り」と「外からの強制」という印象を持たれがちです。
しかし、その本質は組織の活動をより円滑に進めるための“仕組みのサポーター”です。
問題は、それが「難解な文言」で書かれていること。
読みづらく、なじみにくい言葉では、せっかくの内容も形骸化してしまいます。
では、どうすれば現場に定着し、自然と守られるルールへと変えていけるのでしょうか?
その鍵は、“翻訳”と“読み替え”にあります。
1. 交通標識を日本流に変身
ISOMS規格の要求事項は、業務の進行を安全に、かつ効率的に導くための「交通標識」のようなものです。
これについては前回のブログ“ISOMS #007”で述べました。
そのおさらいです。
しかし、その“標識”が外国語で書かれていたら、誰もが戸惑います。
実際、ISOMS規格は英文を日本語に翻訳したものですから、独特な用語や文法が多く、意味がつかみにくいのも無理はありません。
たとえば「力量の検証」や「リスク及び機会」などの言い回しは、現場の感覚と乖離していることがよくあります。
このままの言葉で導入してしまえば、現場からは「何のこと?」と敬遠されてしまうのも当然です。
そこで必要になるのが、“自社用の言葉”への翻訳作業です。
2. 規格文言を“翻訳”して使う
「力量の検証」を「仕事の適正確認」や「スキルの棚卸し」と言い換えるだけで、現場への伝わり方が変わります。
たとえば「是正処置」を「根本原因つぶし」、あるいは「再発防止対策」と表現するほうが、実感に近いかもしれません。
つまり、規格に書かれている文言を、自社の日常業務や職場文化に合わせた言葉に置き換えるのです。
3. 要素の“読み替え”で定着を図る
製造業以外のサービス業などではピンとこないことが多いです。
しかし、視点を変えて「設計=業務計画の立案」「開発=準備と手順の整備」と読み替えれば、あらゆる業種に当てはまる内容に見えてきます。
大切なのは、規格の文言を鵜呑みにするのではなく、「うちの業務で言えば何にあたるか?」という翻訳と解釈の手間を惜しまないことです。
同様に、「品質方針」や「リスク及び機会」といった抽象的な用語も、「お客様との約束」や「職場で起きやすい困りごとと工夫」と読み替えれば、現場の理解と共感が一気に進みます。
4. 自然と守れるルールに昇華する
規格要求事項は、現場の行動を縛るための“檻”ではありません。
むしろ、うまく翻訳・読み替えされた要求事項は、現場にとって「なるほど、これならやりやすい」と感じられる“味方”になります。
そのためには、「これを守れ」と押しつけるのではなく、現場が「守ったほうが楽」「守ったほうが成果が出る」と感じられるようにする必要があります。
具体的には、既存のルールや慣習と重ねて導入し、無理なく自然に使えるようにすること。
そして、使いやすく、優しい言葉で表現しなおすことです。
こうすることで「ルールを守ること」が負担ではなく、当たり前の日常動作として定着していきます。
「ルール」が「ルーティーン」に育てば大成功です。
まとめ
ISOMS規格の要求事項は、「翻訳」と「読み替え」を通して初めて、現場に根づくルールになります。
それは単なる言葉の置き換えではなく、仕組みとして息づかせるための創意工夫です。
難解な要求をそのまま押し込むのではなく、自社の業務・文化・用語に合わせてカスタマイズすることで、
「自然と守れるルール」へと変えていきましょう。
それが、規格を味方に変え、マネジメントシステムを本当に“組織を支え、皆が使える仕組み”へと成熟させる鍵となるのです。
了
By イソ丸研究所
次回は外部審査員との関係性について考えてみましょう。