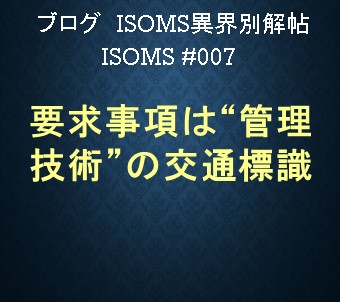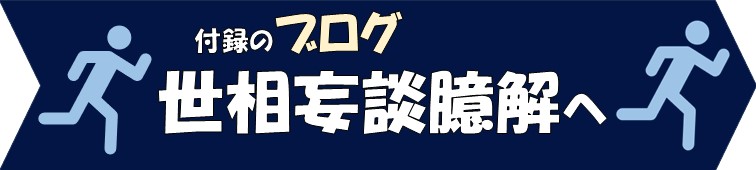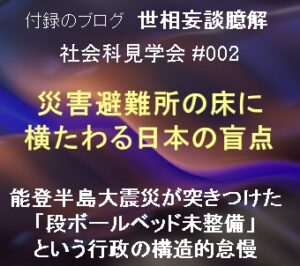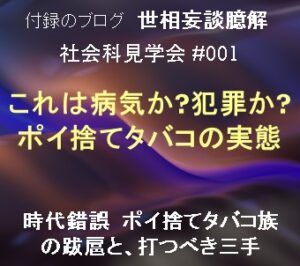ISOMS規格はなぜ生まれた?
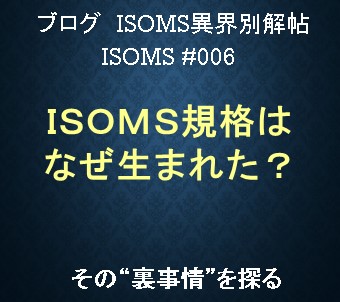
その”裏事情”を探ってみよう ISOMS #006
日夜、イソ活(ISO維持活動の略)にご苦労されている皆さん、
今回はその基にあるISOMS規格の裏側を探りながら、これからのマネジメントシステムを考えてみましょう。
目 次
1. 事実には裏がある。ISO規格も例外ではない。
そもそもこのISOMS(マネジメントシステム)規格とは、どんな背景で作られたのでしょうか。
実はその起源には、英国のしたたかな“戦略”が隠れているという説があります。
1987年にISO 9001が制定される以前、英国では「BS5750」という国家規格がすでに存在していました。
ISO 9001の雛形ともいえるこの規格が、後に巧妙に「国際規格」へと姿を変えたのです。
その裏の仕掛け人とされるのが、あの「鉄の女」サッチャー首相。
QC・TQCでの世界の品質リーダーは日本でした。
「固有技術」では勝てないと見切りをつけた英国は、“品質の仕組み”という抽象的かつ制度化しやすい管理技術で世界市場の主導権を握ろうとした――というのが通説です。
単なる規格ではなく、そこに「認定機関+認証機関」という仕組みを組み込みました。
それに“権威性と客観性”をも付加したシステム戦略は見事なものでした。
以降、顧客が取引先にISO認証の有無を要求する流れが広がり、世界中の産業界が翻弄されていくことになります。

2. ISOは昭和の「黒船来襲」だった!
特にISO 9000's:1994の登場は、日本の製造業界にとってまさに“黒船襲来”。
国内には対応可能な審査機関も少なく、ISO監査員の数も限られていました。
JIS・Q規格の翻訳文も難解で、現場の担当者は「shall(~しなければならない)」の連呼に日々震え上がったものです。
その中で始まったISOMS審査は「規格適合」審査として、規格文言の一言一句まで適合しているかを厳格に見られるものでした。
審査期間中は、まさに“お上のお裁き”といった様相。
審査員も何ゆえにか“伝説的な”こわもてぞろいで、「この審査員が来たら撃沈を覚悟しろ」と語られるような事例も多くありました。
本来の現場の仕組みやその組織の文化よりも、ISO規格文言への形式的で完璧な符合が重視される審査内容でした。
そんな強烈な“外圧”の中で、多くの企業が「ISOのための活動」に多大な疑問を抱きながらもISO認証取得とその更新作業に追い込まれていきます。
3. 変わり始めた審査の視点
しかし、2008年以降から風向きが変わります。
ISOMS審査が「プロセス・アプローチ」審査方式へと転換します。
規格の条文にぴったり合っているかよりも、組織内のプロセスが機能しているか/成果が出ているかを重視する審査へと移っていきます。
つまり、ISOの用語や表現そのものよりも、実際にどう動いているか、どう繋がっているかを見る。
これは大きな転進と進化であり、ようやく業務の“実態”に即した評価が始まったといえるでしょう。
とはいえ、導入当初の“黒船ショック”の記憶はまだ根強く、ISOMSに対して「面倒」「うるさい」「役に立たない」といった声が残るのも無理はありません。
形式的な「審査対応」がいまだに慣習化している企業もあります。

4. 最後に:ISOMSは「国家戦略」であり「国際戦略」だ?!
要するに、ISOMS規格の成立は、単なる“善意のグローバルルール”ではなく、明確な戦略意図のもとに形成されてきた制度なのです。
そして、その制度に対応する中で、日本の現場は少なからぬ誤解と過剰適応を繰り返してきました。
審査員の言葉に振り回され、現場のプロセスが変形させられ、組織の自然な成長を阻害する――そんなことすら起きていたのです。
それでも、現代のISOMS審査は変わりつつあります。
組織本来の活動と成果を重視する視点がようやく根付きつつある今、過去の“幻影”を脱ぎ捨て、本来あるべきISO活(イソ活)へ舵を切る時が来ています。
次回は、本ブログ続編の「要求事項とは“管理技術”の交通標識である」 乞うご期待!!
(了)
By イソ丸研究所