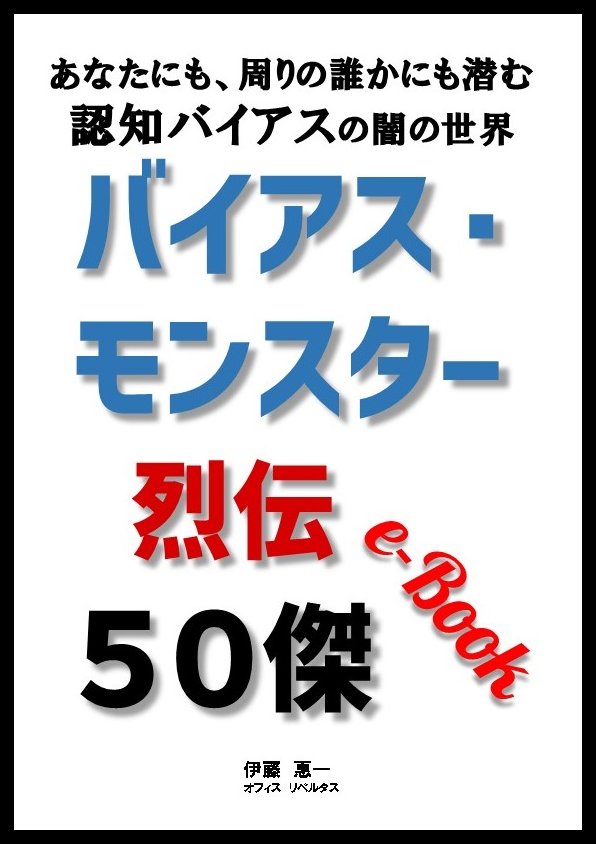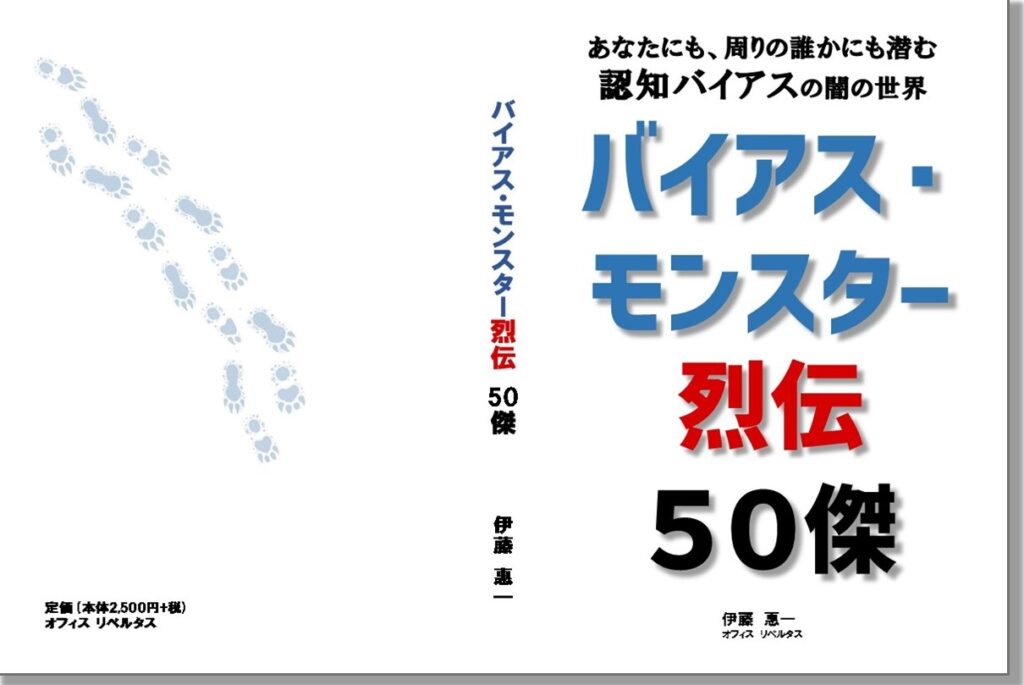認知バイアス、知ってます?

認知バイアスと心理メカニズムを探ってみる
目 次
はじめに
「心理メカニズム」と「認知バイアス」と言う二つの言葉を皆さんはご存じですか?
古くから心理学や行動経済学で取り上げられる用語ですが、あまり馴染みがないのが実情です。
ところがこの二つの言葉には私たち自身だけでなく、さまざまなニュースのもととなる事件や出来事を動かす力を持つ世界が秘められています。
その世界は心と脳にあるのです。
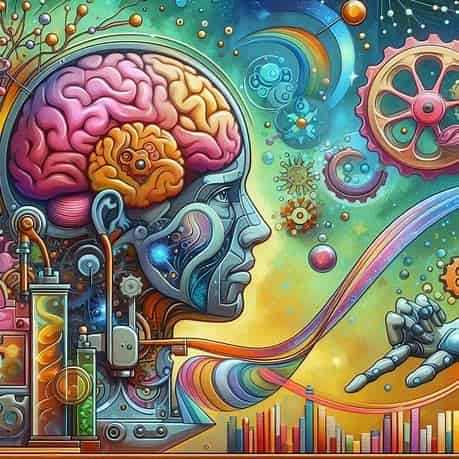
これらの世界を知り、理解することは、これからの人生に必ずプラスの効果をもたらすと思います。
そこでまず簡単に二つの世界を説明すると、
「心理メカニズム」: 人間の行動や感情、思考の背後にある心の自動機械的な働きやそのプロセスを指します。
これらのメカニズムは、私たちの日常生活や社会的な行動に深く関与しています。
「認知バイアス」: 上記の心理メカニズムが働くときに生じる「思考の歪み」(敵意を感じる、都合よく解釈する など)。
心理メカニズムと認知バイアスには、ある種の因果関係が互いに存在する場合が多くあります。
1. 「認知」とは何か?
「認知」と言えば、「認知症」と言う病気を皆さんは頭に思い浮かべるでしょう。
その病名に冠せられた「認知」とは、感覚、感情、思考、思想などを含めた個々人が抱く情報処理を指しています。
まさにその複雑な情報処理システムが壊れていく病気だから「認知症」なんですね。
私たちは日々、論理的で冷静な判断をしているつもりでも、実際にはさまざまな心理メカニズムに動かされ、また種々の認知バイアスに影響を受けています。
認知バイアスには良い面もあれば、悪い面も合わせ持っています。

筆者は良い面を「バイアス・ヒーロー」、悪い面を「バイアス・モンスター」と勝手に名付けています。
仕事でも、プライベートでも、いつの間にかにバイアス・モンスターの影響を受け、誤った判断を下したり、他者との摩擦を生んだりしてしまうことに従来から警鐘を鳴らしています。
では、なぜ私たちは時にこのバイアス・モンスターに変身してしまうのでしょうか?
その背景には、私たちの心理メカニズムが深く関係しています。
2. 心理メカニズムの主要な働き
心理メカニズムには大別すると3つの働きがあることが分かっています。
順に概説していきましょう。
2-1. 心理メカニズムが情報処理の「土台」となる
私たちの脳は、外界から絶えず膨大な情報を受け取っています。
これらの情報を効率的に処理し、意味のあるものとして理解するために、次のようなメカニズムが働いています。
a) 情報の選択: 全ての情報を均等に処理することは不可能なので、重要な情報とそうでない情報を 選択します。
b) 情報の整理: 選択された情報を、記憶や知識と照らし合わせ、整理します。
c) 情報の解釈: 整理された情報を、個人の経験、価値観、信念などに基づいて解釈します。
これらの心理メカニズムは、私たちが現実を認識し、理解するための 基本的な枠組み を提供します。
しかし、必ずしも客観的で論理的な判断が保証されるわけでは無いのが問題となります。

2-2. 心理メカニズムの「効率化」が認知バイアスを生み出す
心理メカニズムは、情報処理を効率化するために、認知的ショートカット(ヒューリスティックス=経験則) を利用します。
ヒューリスティックスは、迅速な判断を可能にする一方で、特定の状況下では思考の偏り、つまり認知バイアスを生み出す原因ともなります。
a) 情報の簡略化: 複雑な情報を効率的に処理するために、詳細な分析を省略したり、ステレオタイプに頼ったりすることで、判断の偏りが生じます。
b) 感情の影響: 感情は、意思決定に大きな影響を与える心理メカニズムです。感情的な反応が、客観的な情報処理よりも優先されることで、認知バイアスが生じます。
c) 過去の経験の重視: 過去の経験に基づいて未来を予測したり、判断したりする際、その経験が現在の情報解釈や未来予測に過度に影響を与えて偏った判断を生みます。
これらのヒューリスティックスは役に立つ反面、必ずしも論理的で客観的な推論に基づいていない危険性があります。
2-3. 心理メカニズムの「結果」として認知バイアスを産み出す
心理メカニズムという土壌の上に、認知バイアスという花が咲くイメージです。
a) 利用可能性バイアス: これは、利用可能性ヒューリスティック という、記憶の中で想起しやすい情報に基づいて判断する心理メカニズムの結果として生じる認知バイアスです。
b) 確証バイアス: これは、自分の信念を支持する情報を優先的に探し、受け入れるという 確証バイアス (メカニズムとしての側面) の働きによって生じる認知バイアスです。 (認知バイアスとしての確証バイアス)
c) 損失回避バイアス: これは、損失回避 という、利益を得るよりも損失を避けることを優先する心理メカニズムの結果として生じる認知バイアスです。
このように、認知バイアスは、特定の心理メカニズムが作動した結果として、必然的に生じる思考の偏りと言えます。
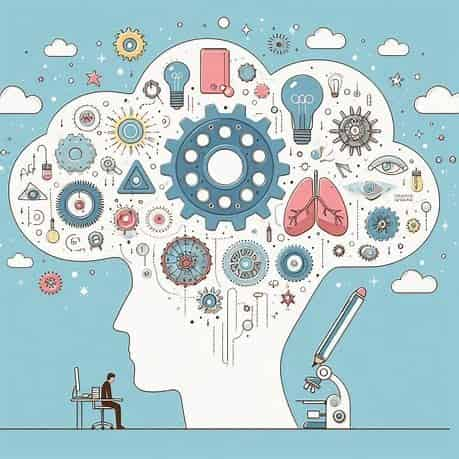
心理メカニズムというコインの表(原因)があるからこそ、認知バイアスというコインの裏(結果)が存在するとも言えます。
だいぶ専門的な内容になってきましたが、日常生活の中で意識するためにも必須な知識として覚えておくと良いでしょう。
3. 自己防衛本能が生む認知バイアス
動物の脳は、太古の昔から種々の危険を回避し生存していくために発達してきました。
その結果、自己防衛のためのいろいろな認知バイアスがi生まれます。
- 正常性バイアス:危機的な状況でも「大丈夫だろう」と楽観的に捉え、適切な対応を取らない。
- 敵意帰属バイアス:他者の行動を敵対的と解釈しやすくなる。
- 確証バイアス:自分の信じたい情報だけを集め、都合の悪い事実を無視する。
職場で新しい業務改善策が提案されたとき、「これまでのやり方で問題なかった」と思い込み、猛烈に反論するのは「確証バイアス」のモンスター化の一例です。
また、会議で意見が対立した際に「相手が自分を攻撃している」と感じ、敵意を剥き出しにするのは、「敵意帰属バイアス」モンスター化の影響と言えます。
毎日、どこかであるあるの話ですね。
4. 社会的影響による認知バイアスの強化
認知バイアスは個人の心理だけでなく、社会的・集団的な環境要因によっても強化されます。
- 同調バイアス:多数派の意見に流されやすくなる。
- ホーン効果:一つのネガティブな特徴から、相手全体を否定的に評価してしまう。
会議で周りの人が皆賛成していると、自分も意見を変えて賛成してしまうのは同調バイアスの影響です。
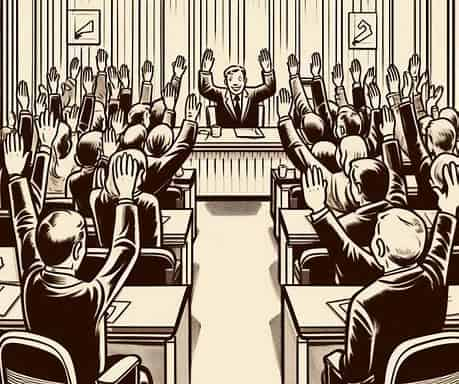
また盛り付けが雑な料理が出されるとどれもマズそうと感じるのは、まさに「ホーン効果」モンスターが暴れまわっている証拠です。
5. バイアス・モンスターから逃げ出すには
認知バイアスは私たちの心の中から完全に無くすことはできません。
でもその存在を理解し、自覚してコントロールすることは可能です。
心理メカニズムの一つで次の有名な「思考のパターン理論」があります。
5-1. システム1とシステム2:思考の二重構造
二つの異なるシステムで私たちの認知活動が展開されているとする理論です。
- システム1(直感的思考/直感):瞬時に反応する自動的で素早い思考プロセス。感情や経験に基づく判断を下す。
- システム2(熟考的思考/理性):論理的に考え、時間をかけて慎重に判断するプロセス。

多くの認知バイアスは、この「システム1」によって生まれます。
例えば、第一印象で相手を判断する「代表性ヒューリスティック」や、目の前の情報に強く影響される「アンカリング効果」などの認知バイアスがその典型です。
システム1が誤った結論を出しても、システム2が介入しない限り、そのまま認知バイアスに基づいた行動を取ってしまいます。
一般的に動物本来の生存本能で、脳はエネルギー消費を抑えるためにできるだけシステム1を使おうとするためです。
その結果、「バイアス・モンスター」の出現を招き、偏った判断から悪い結果を招くことになります。
5-2. 「思考のパターン理論」を使いこなそう
a) システム2を意識的に使ってみる
システム2は前項で解説した通り「熟考的思考/理性」システムですから、論理的に考える習慣として『これはシステム1の判断ではないか?』と必ず自問してみることをお勧めします。
b) 多角的な視点を持とう
周囲の異なる多くの意見を意識的に取り入れ、確証バイアス・モンスターを防ぐ。
c) 感情に流されない
特に重要な決断をするときは一度、間をおいて冷静になり、信頼性の高いデータや事実を基に考える。
d) 環境を整えよう
バンドワゴン効果(社会的証明)や同調バイアス・モンスターを避けるため、偏った情報源に頼らず、多様な意見に触れる。
e) フィードバックを集めて活用する
他者からの客観的な意見を積極的に求め、自分のバイアス・モンスターに気づくことができる。
まとめ
認知心理学や行動経済学の研究が進み、現在では数百から数千の心理メカニズムが人間の行動に影響を与えていると言われています。
また認知バイアスは300種を超えて観察されているそうです。
その認知バイアスには良い面、悪しき面の両方があります。
悪しき面が表出したバイアス・モンスターは誰の中にも潜んでいます。
その正体を知り、またその素にもなる心理メカニズムも共に理解することで、誤った言動や行動を防ぐことができます。
私たちの生活や仕事の中で、どのような認知バイアスが影響し、他者や自分がモンスター化しているのかを意識しながら、より客観的で柔軟な思考をもとに実り豊かな人生を目指しましょう。
雑話ブログ「時游神の痕跡」では、この”Health”や”Society”のエリアなどで日々の生活や人生の中に出現する具体的な認知バイアス及び心理メカニズムの事例や対策についてさらに深掘りしてお伝えしていきます。
またモンスター化した代表的な認知バイアスを50種集めて「バイアス・モンスター烈伝 50傑」をKindleより出版しています。
このブログにも出てきたバイアス・モンスターがリアルな肖像と共にいろいろ解説されています。
書籍のご案内は「KINDLE界隈」でもご覧いただけます。
どうぞお立ち寄りください。
了
参禅寺 源吾