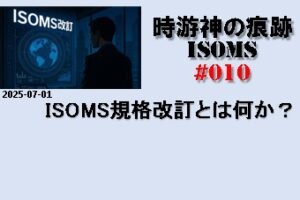初夏の、ほおずき市だよ
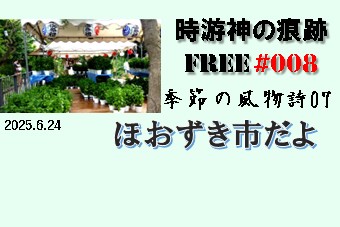
季節の風物詩を求めて その7 FREE #008
目 次
1. はじめに
東京都港区にそびえる愛宕山、その頂に鎮座する愛宕神社で開かれた初夏の風物詩の一つ、「ほおずき市」を訪れました。
江戸時代から続くこの市は、都会の喧騒の中にありながら、日本の庶民文化の奥深さ、変わり行く時の流れ、それと変わらない人々の情をそれぞれに感じさせてくれる貴重な存在です。
この場所で催される初夏の出来事は、単なる年中行事に留まらず、その土地の歴史や人々の営みに触れられる貴重な体験となります。

2. 愛宕山と「出世の石段」
港区虎ノ門近くにある愛宕山は、標高25.7m または26m と低いながらも、東京都23区内で自然の地形としては最も高い山として知られています。
少しその歴史を遡ってみましょう。
古くは京都市右京区嵯峨にある愛宕神社が本社とされ 、江戸の愛宕神社は徳川家康公の命により1603年(慶長8年)に防火の神様として建立されたのが始まりです。
もともと「桜田山」と呼ばれていたこの地は、愛宕神社が建立されて以降「愛宕山」と改名されました。
家康は戦乱の世では軍神として愛宕権現を信仰しましたが、太平の世では江戸鎮護の火防の神として祀った背景には、時代の移り変わりと共に神社の役割が変化し、人々の願いに応える形でその存在意義を深めてきた歴史が垣間見えます。


この石段は、寛永11年(1634年)に三代将軍家光公が愛宕山の梅を所望した際、曲垣平九郎(まがき・へいくろう)が見事、馬に乗ってこの急な石段を駆け上がり、梅を献上したという故事に由来します 。
歩いて登り降りするのも困難なほどの急勾配を、馬で駆け上がったというこの無謀とも思える挑戦を成功させた逸話が琵琶法師や講談師の創作話から広まり、この石段は「出世」のご利益があるとされ、現代でも志を秘めたビジネスパーソンが成功を願って石段を登ります。
実際に登ってみると、その急勾配に息をのむほどですが、一歩一歩踏みしめるごとにこの石段は単なる物理的な階段ではなく、歴史的な物語と個人の願望が結びつく象徴的な道程であり、その物語が現代に生きる人々の心に響き続ける文化的な関りを示しているようにも感じます。
拝殿の左手には、平九郎が家光公に献上したと言われる梅の木も残されています。

3. 清らかな境内と「茅の輪くぐり」の祈り
小山とはいえ、この急な石段を登りきると、そこには都心とは思えないほど清々しい境内が広がります。ここ数年で境内は整備され、「こざっぱりとした感じ」がしました。
実際、愛宕神社では令和5年11月頃から令和6年の春ごろまで大規模な境内整備が行われており、以前は地面の穴の中にあった三角点や水面下で見えなかった日本最古の三角点もリニューアルされたようです。
整備されたお池には色鮮やかな鯉が出迎えてくれます。
本殿の手前では、夏の厄除けとして「茅の輪くぐり」が設けられていました。
これは「夏越の祓(なごしのはらえ)」という伝統的な神事の一環で、茅(ちがや)という植物で作られた大きな輪をくぐることで、半年間の穢れを祓い、疫病退散や無病息災を願うものです。

その由来は日本神話の蘇民将来(そみんしょうらい)の伝承にあり、スサノオノミコトが貧しいながらも快く宿を提供してくれた蘇民将来に感謝し、茅の輪を渡して疫病から免れる術を教えたとされています。
本来は、「水無月(みなづき)の夏越の祓する人はちとせの命のぶというなり」という古歌を心で唱えながら、左回り、右回り、左回りと八の字を描くように三度くぐり抜ける作法で、伝統行事の奥深さを感じさせます。
ほおずき市が開催される千日詣りの日に茅の輪が設置されることは 、まさにこの時期が心身を清め、新たな半年を迎えるための重要な節目であることを示しており、古くからの信仰と季節の移ろいが現代にも息づいていることを象徴しています。
4. 「ほおずき市」の歴史と文化
「ほおずき市」は、日本全国で夏の訪れを告げる代表的な風物詩の一つです 。
鮮やかなオレンジ色の果実を提灯に見立て、お盆に飾る風習は、ご先祖様の足元を照らす灯りや、家の場所を知らせる灯りとしての意味合いを持ちます。
また、玄関に飾って魔除けや病除けとしたり、さらには風水的に金運アップや豊穣の象徴としても親しまれてきました。
その花言葉には「自然美」や「心の平安」があり 、その独特のフォルムを提灯と見立てたのは、古代からの自然への崇敬の念と言えます。

ところで愛宕神社のほおずき市は、その発祥の地として特別な意味を持ちます。
江戸の昔、愛宕神社では毎年6月23日と24日の両日に「千日詣(せんにちもうで)」が行われていました。
この日に参拝すると千日分のご利益があるとされる功徳日であり、この時期に境内で売られていた青ほおずきを飲むと、子供の虫封じや女性の病気に効くという神様のお告げの夢が評判となり、市が立つようになったのが始まりと伝えられています。
現在では浅草寺のほおずき市が盛大かつ有名ですが、愛宕神社こそがそのルーツであることは地域の誇りと言えます。
今年のほおずき市では、多くの鉢植えのホオズキの実はまだ青く、赤く染まったものはちらほらとしか見られませんでした。
しかし、これこそが前述の通り、この時期に売られる意味があります。
青ほおずきであることが「これからの色変わりが楽しみ」という期待感を抱かせます。
青い実が徐々に赤く色づいていく様子は、初夏から朱夏の深まりと共に変化する自然の美しさを象徴しているかのようです。
ほおずきが「豊穣の象徴」とされることを鑑みれば、この未熟な状態はこれからの豊かな実りを予感させる、希望に満ちたワンシーンとも言えるでしょう。
一方で、ほおずきの内部が空洞であることから「偽り」「ごまかし」といった花言葉も存在し、過去には子宮を収縮させる毒性を利用して堕胎目的で利用されたという怖い側面も持ち合わせていました。
しかし、現代ではその美しい形状と初夏の風情を象徴する存在として、多くの人々に愛されていることは間違いありません。


愛宕神社以外にも様々な場所でほおずき市が毎年開催され、その地域で夏の風物詩として親しまれています。
関東地方に限って言えば、主なほおずき市の開催は次の通りです。
(詳しくは、それぞれのリンク先でご確認ください)
・愛宕神社 (港区) | 6月23日・24日 | 発祥の地 | 千日詣り
・浅草寺 (台東区) | 7月9日・10日 | 四万六千日
・龍泉寺 (茨城県龍ヶ崎市) | 7月10日 | 龍ケ崎観音がある | 四万六千日
・出雲大社相模分祠 (神奈川県秦野市) | 7月12日・13日 | 夏詣の一環
・源覚寺 (文京区) | 7月19日・20日 | こんにゃく閻魔で有名
5. ほおずきが彩る風物詩の魅力
愛宕神社のほおずき市は、まさに日本の「初夏の風物詩」を見事に体現しています。
急な石段を登り、茅の輪をくぐり、そして境内の賑わいの中で青々としたほおずきを眺めるこれらの体験は、五感を通して「初夏」という季節を強く印象づけます。
残念なのは、今年の梅雨がやたら梅雨らしくなく、まったく雨のない日が激暑の中で続いていることです。
それでも境内に多くの人々が行き交う活気は、都市の喧騒を忘れさせ、古き良き江戸の風情へと誘います。
そしてオレンジに染まっていくほおずきの色は、提灯のようにこれからの夏の夜をほんのり照らし、お盆の時期にはご先祖様への思いを馳せるきっかけとなります。

これらの要素が複合的に作用し、視覚、聴覚、そして文化的な記憶が一体となることで、この風物詩は単なる季節の象徴を超えた、豊かな文化的体験となるのです。
このような伝統行事が現代に受け継がれ、多くの人々に親しまれていることは、日本の文化の豊かさと、季節の移ろいを大切にする心の表れです。
特に、愛宕神社のように都心にあり、周囲を超高層ビルに取り囲まれながらも自然の豊かさを保ち、「都心のオアシス」として機能している場所は、現代社会において人々が日常から離れ、心安らぐ時間を見つけるための貴重な存在と言えます。
また、罪穢れを祓い清める「夏越の大祓」を経て、無事に半年を過ごすことへの感謝と更なる平穏を願うため、7月1日以降にも神社・仏閣に参拝します。
この習慣を「夏詣」と称し、全国の神社・仏閣に広まりつつある新しい習わしが加わることで、従来の伝統が時代に合わせて形を変えながらも、その本質的な魅力を失わずに受け継がれていく様子も見て取れます。
これは、文化が常に変化し、進化する生きたものであることの証左と言えるでしょう。
6. 結びに:心に残る夏の記憶
初夏の行事である愛宕神社のほおずき市は今年も心に残る時間となりました。
江戸時代から続く歴史の重み、「出世の石段」に込められた人々の願い、「茅の輪くぐり」で清められた心、そして鮮やかな青々としたほおずきの鉢植えが織りなす夏の初めの彩り。
これら全てが溶け合う伝統の重みが現代にも引き継がれている面白さを教えてくれました。

まだ青いほおずきの実が、これからそれぞれの家庭で赤く染まっていくように、私たち自身もまた、季節の移ろいの中で新たな発見や喜びを手にしましょう。
この自然のサイクルに身を委ね、その変化を楽しむ心こそが、日本の「風物詩」が教えてくれる大切なことなのかもしれません。
それは、絶え間ない様々な変化を受け入れつつ、その中に美しさや希望を見出し、新たな日本文化を紡いでいく豊かな精神性とも言えるでしょう。
どうですか?身近な「季節の風物詩」に触れる小さな旅散歩に出かけてみてはいかがでしょうか。
きっと、都会の喧騒を忘れ、心豊かなひとときを過ごせるはずです。その体験が、一人ひとりにとっての「心に残る今年の夏の記憶」となることを願ってやみません。
了
*注)本ブログ中の日本画は、琵琶曲図書館HP掲載の「間垣平九郎像(月岡芳年画)」を借用させていただきました。
皆戸 柴三郎