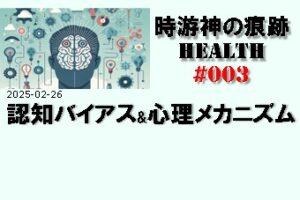街に春の香りが漂った

季節の風物詩を求めて その4 FREE #005
目 次
はじめに
いつもとは違う散歩道を歩いていたら、かぐわしい香りに包まれました。
ふとビルのかたわらに造られた花壇に目をやると、幾つかの植栽の中に小さな蕾と花弁を束ねたような花が咲いていました。
春先に強い芳香を放つ花を咲かせる常緑低木の沈丁花(ジンチョウゲ)です。
「ちんちょうげ」と呼ぶ人もいますが、『じんちょうげ』が正解です。
ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属で、学名は〝Daphne odora“と命名されています。
東京ではおおむね2月中旬から咲き出すこの花の香りと匂いで、春の到来がすぐそこまでと感じられる貴重な香木です。
今回は、この沈丁花を春の風物としてお話ししていきましょう。
1. まずは植物学的なことから
この植物の原産地は中国の南部です。
それゆえ寒さに弱く、耐寒性はマイナス5度程度です。
東北や北海道のような寒冷地では、きっと屋外ではあまり見かけない花かもしれません。
日本には室町時代以降に伝わり庭木として広く栽培され、後述しますがその香りが珍重されています。
花の特徴として小さな花が集まった丸い形をしており、赤紫色(外側が濃く内側が白)のものが一般的ですが、白花品種(シロバナジンチョウゲ)もあります。

低木の常緑樹ですから、その楕円形の葉は一年中革質で光沢があります。。
甘く強い香りが特徴で、「三大香木」(ジンチョウゲ、クチナシ、キンモクセイ)のひとつに数えられます。
さてその名前の由来が風雅なんですね。
花の香りが香料となる「沈香」と「丁子」に似て、その二つがミックスされていることから名付けられました。
「沈香(じんこう)」と「丁子(ちょうじ)」はどちらもポピュラーな香木で、我が国でも『お香』として用いられています。
先に学名が〝Daphne odora“となっていると述べましたが、英語名では「Winter Daphne」や「Fragrant Daphne」と呼ばれます。
この名前は、沈丁花が冬から早春にかけて花を咲かせ、その香りが非常に強いことに由来しています。
ところで"Daphne" とは何でしょう?
これはギリシャ神話に由来しますが、その神話の中で、ダフネ(Daphne)は美しいニンフ(精霊)であり、アポロン神の誘惑から逃れるために月桂樹に変身したという伝説があります。
この伝説から、"Daphne" は月桂樹を意味し、植物の名前としても使われるようになりました。
沈丁花の学名の通り、強い香りを持つ美しい花として欧米でもよく知られています。
春先に香り高い花を咲かせることから、その花言葉は希望や永続する美しさを表す「栄光」「不滅」「優雅」などが当てはめられています。
2. 香りがいざなう文学性
甘く優雅な香りを放ち、春の訪れを告げる沈丁花の花は、古くから人々に愛され、詩や文学の中にもその姿を残しています。
日本文学における沈丁花の描かれ方を探ってみましょう。
その前に沈丁花の原産地は中国ですから、御当地ではどうでしょうか?
2-1. 蘇軾が愛した沈丁花
当然のことながら原産国である中国でも、古くから香りの良い植物として珍重されてきました。
しかし、中国では「沈丁花」という名前ではなく、「瑞香(ずいこう)」と呼ばれます。
特に、宋代(960年 - 1279年)の詩人たちはその香りを「高潔さ」や「永遠の美」に例えました。
例えば、その宋代随一の文豪であった蘇軾(そしょく/1036-1101年) はこの瑞香をモデルに次のような「瑞香詩」を詠みました。
瑞香天賦美,未肯媚春風。瑞香 天賦の美あり,未だ肯えて春風に媚びず。
淑氣潤幽茎,良辰増玉容。淑気 幽茎を潤し,良辰 玉容を増す。
芳心絶塵欲,翠葉含霜濃。芳心 塵欲を絶ち,翠葉 霜を含んで濃し。
老子同相親,持之供酒翁。老子 同じく相親しみ,これを持して酒翁に供す。
これを訳すると、
「瑞香(ずいこう)」という花は、生まれつき美しく、決して春風に媚びることはない。
清らかな気がそのひっそりとした茎を潤し、良い日和がさらにその玉のような美しさを引き立てる。
芳しい心は俗世の欲望とは無縁であり、緑の葉は霜を含んで一層濃く輝く。
私(老子)はこの花と親しみを感じ、これを摘んで酒好きの老人に捧げよう。
この詩では、瑞香の花が持つ天賦の美しさを讃え、その香りや姿が春の風に媚びることなく、自身の存在感を持ち続ける様子が描かれています。
また、瑞香の持つ清らかな香りと翠葉の美しさを表現し、また友人と共に沈丁花を愛でながら時を過ごす喜びを伝えているのだそうです。
2-2. 日本文学に咲く沈丁花
日本では、沈丁花は室町時代以降に文献に登場するようになります。
江戸時代の俳句の中で盛んに「春の香りの象徴」として詠まれています。
「沈丁の ふくるる香り 夕まぐれ」
江戸時代の歌人 加賀千代女(かがのちよじょ)が読んだ句からは、沈丁花の香りが日暮れとともに広がり、静かな情景を作り出す様子が伝わります。
現代短歌では、次の有名な二人の歌人が沈丁花を読んでいます。
・佐佐木信綱 - 「若き日の 夢はうかびく 沈丁花 やみのさ庭に 香のただよへば」
・若山牧水 - 「沈丁花 青くかをれり すさみゆく 若きいのちの なつかしきゆふべ」

また現代俳句でも沈丁花を題材にしたものが多くあります。
今井つる女 - 「ある日ふと 沈丁の香の 庭となる」
阿部みどり女 - 「一握の 雪沈丁に 日脚のぶ」
稲畑汀子 - 「一片を 解き沈丁の 香となりぬ」
高野素十 - 「冴え返る 二三日あり 沈丁花」
野村泊月 - 「沈丁に 雨だれしげく なりにけり」
2-3. 沈丁花の香りが持つ象徴性
沈丁花の香りは、文学の中でしばしば 「記憶」や「余韻」 の象徴として扱われます。
遠くまで届く香り → 人の想いが伝わる
春の訪れとともに香る → 新しい出発、再生の象徴
強く長く残る香り → 儚くも永遠に残るもの
このように、沈丁花は単なる美しい花ではなく、人々の心に残る「余韻」として当時の詩の中で語られてきました。
まとめ
今年の冬は日本海側に近年まれな豪雪をもたらし、春はまだまだ先の模様。
ところが関東は寒暖の差が激しいものの、春の本格的訪れを示す桜開花は早く、3月20日前後とか。
その3月はまもなく「桃の節句」のひな祭りが催され、これも春の来訪を告げる風物詩でもあります。
でも春の夕暮れに沈丁花の香りを感じたとき、古の詩人や歌人たちの詩歌に託した想いに心を巡らせるのも、また風流な春の楽しみ方かもしれません。
どこかで沈丁花の香りを感じたら、ぜひ一篇の詩や俳句でも詠んでみてはいかがでしょうか。

ところで沈丁花はむやみに樹や赤い実などに触っては駄目ですよ!
この沈丁花には、赤い実や根、さらには樹液にも毒素が含まれています。
樹皮や樹液に直接触れた場合、皮膚にかゆみや水ぶくれが生じるリスクがあります。
また、沈丁花の実を誤って摂取した場合、下痢や嘔吐はもちろん、最悪のケースでは心臓に影響を及ぼす可能性も考えられるそうです。
ご自宅のお庭で沈丁花の手入れをするときには必ず手袋を着用するようにしましょう。
特に、お子さんや犬、猫がいるご家庭では、沈丁花が容易に触れられない場所に植えるなど、リスクを避けることが大切です。
(了)
皆戸 柴三郎