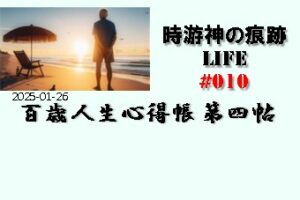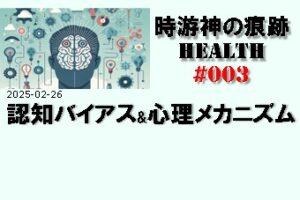梅まつりに出掛けてみた

季節の風物詩を求めて その3 FREE #004
目 次
◐ はじめに
季節ごとに巡り合う風物詩をいろいろ書き連ねようとしていましたが、いつの間にか大晦日も正月も過ぎてしまい、節分と立春もぼーっと過ごして絶好の季節ネタを取りこぼしてしまいました。
これも老化のなせる業でしょうか?
それはともかく2月も中ほどになると温かな日差しを感じる日がちらほら。
散歩コースの芝公園で今年も梅まつりを催しているようなので春を迎える風物詩として「観梅」に出掛けてみました。
◑ 芝公園の梅まつり
以前に芝公園を散策している折に「梅まつり」開催の案内板を見つけました。

2月15日土曜日のたった一日の開催ですが、冬の終わりの風物詩として出かけました。
ただ芝公園の梅林はこの後に掲げた観梅の名所とは比較にならない小規模なものです。

上図は芝公園の概略図ですが、緑色部が公園で、増上寺と東京プリンスホテルを取り囲んでいます。
江戸時代は増上寺境内であった敷地を明治以降に恩賜公園としたのですが、左下部の赤い丸印の中に梅林があります。
ここは芝公園の1号地と呼ばれるところです。
本当に小さな小さなエリアに梅の木が点在しています。
公称70本ですが、実は老木もあり、60数本に減っています。
9種類の梅が風雪に耐えて今年も可憐な花を開き、観る者の目を楽しませてくれます。
紅梅、白梅、黄梅など可憐な花々が野趣をそそります。
近くにある港区役所の管理チームの方々がテントを張って、訪れる観光客を迎えていました。
以前は確か野点(のだて)も行われていて、華やかな和服姿の茶人がお茶を点てていましたが、今年は無いとのことでした。



ご覧の通り、ささやかな梅の木立が立ち並ぶ光景ですが、それなりの人々の観梅で賑わっていました。
春の風情を楽しむ豊かな心が伝わってきます。
案内板に「銀世界」と銘打ってありますが、園内に真っ白な白梅が溢れているわけではありません。
江戸時代、現在の新宿三丁目あたりに「梅屋敷銀世界」と言う梅園があり、その地から明治末期に梅の木を移植したいわれでその名を受け継いでいるとのこと。
余談ですが、「梅屋敷」と言えば、『蒲田梅屋敷』も江戸時代から有名な観光地でした。
現在、京浜急行線の駅名として残っている梅屋敷がそれです。
興味のある方は、こちらの『梅屋敷探検隊』のHPをご覧ください。

ところで「梅に鶯(うぐいす)」と言う言葉がありますが、なんと初めてその光景を目にすることができました。
下の画像がそれです。

この鳥、鶯ですよね?
それとも、メジロでしょうか?
都会のど真ん中に生息すると言ったら、ウグイスよりもメジロに軍配が上がるでしょうね。
梅の花にくちばしを突っ込んで蜜を吸っているようでした。
メジロであれウグイスであれ、これは眼福です。生涯で初めての目撃談ですから。
◓ 梅祭りのあれこれ
★ 梅祭りの歴史
芝公園の梅まつりは小規模で、壮観さには欠けますが、それでも梅見の風情を十分に感じることができました。
ところでこの梅祭りはいつ頃から日本文化を飾るようになったのでしょうか?
実は梅祭りのベースとなるのが「観梅」の習慣です。
梅を愛でることは奈良時代及び平安時代初期における宮廷貴族のステータスであり、遊びの一つでした。
なにしろ梅自体が中国からの高級舶来品で、日本には無かったのです。

本格的な「観梅」はなんと江戸時代の後期。
1842年(天保13年)に第9代水戸藩主・徳川斉昭公が造った庭園の『偕楽園』で、当の徳川斉昭公が梅の木を多く植えました。

梅の花が冬の寒さに耐え、春に先駆けて咲く姿に感銘を受けたことが梅の植栽の動機だったとか。
これが現在の梅まつりの原点とされています。
その後、明治時代に鉄道が開通し、観梅の面白味が広まり、多くの観光客が訪れるようになり、それから全国に広まっていきました。
★ 梅祭りの名所
関東及び東京に限って言えば、次に挙げる場所が梅の名所で梅祭りも盛んです。
《関東》
- 偕楽園(茨城県):2025年2月11日(火・祝)~3月20日(木・祝)
- 坂田城跡梅林(千葉県):2025年2月22日(土)~3月9日(日)
- 観音山梅の里梅園(栃木県):2025年3月9日(日)~16日(日)
- 榛名梅林(群馬県):2025年3月中旬~2025年3月下旬
- 曽我梅林(神奈川県):2025年2月1日(土)~2月24日(月・祝)
- 越生梅林(埼玉県):2025年2月15日(土)~3月16日(日)
《東京》
- 湯島天神:2025年2月8日(土)〜3月9日(日)
- 高尾梅郷:2025年3月8日(土)・9日(日)
これらはごく一部の名の知れた場所に過ぎません。
皆さんの身近な公園や庭園でも、きっと毎年開催されているところがあるのでは。
春のさきがけを感じるためにもご近所の梅祭りを探されて足を運ぶのも一興です。
きっと絵心をくすぐられるかもしれません。

◎ おわりに
春先の花と言えば、梅、桃、あんず、桜がその色合いの美しさで競い合います。
特に桜は日本人の心情に溶け込んで、さまざまな物語を奏でますが、奈良、平安初期に愛された梅とは違い、平安後期以降に人気を博することになります。
例えば和歌のモチーフで観ると、万葉集では梅119首、桜47首で梅の勝ち。
ところが新古今和歌集では梅17首、桜85首と桜が大逆転。
『源氏物語』や『枕草子』などの文学の隆盛と、武士階級の台頭で日本人の美意識が変化していきます。
それでも梅の美しさは変わることなく、こうして千年の時空を超えて愛されていることを考えると、なぜか嬉しくなります。

天平2(730)年、万葉歌人の大伴旅人など著名な歌人32名が宴で詠んだとされる「梅花の歌」32首が万葉集に載せられています。
その中から一首。
『春されば まづ咲くやどの梅の花 ひとり見つつや 春日(はるひ)暮らさむ』
☞春が来るとまっ先に咲く庭前の梅の花、この花を、ただひとり見ながら長い春の一日を暮らすことであろうか。
これは「貧窮問答歌」で有名な「山上憶良(やまのうえのおくら)」の歌で、筆者の好きな和歌です。
季節の移り変わりは意識しないとその変化を見逃してしまいます。
ちょっと周りの花や空など景色に目を止めれば、こうしていろいろな感性の冒険ができます。
前述でご紹介した通り、まだまだ梅祭りはさまざまなところで催されています。
休日にお出かけして万葉の歌人気取りで観梅でもしてみましょう。
そして季節の移ろいの美しさと人生を大いに楽しみましょう!
了
皆戸 柴三郎