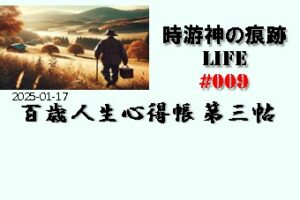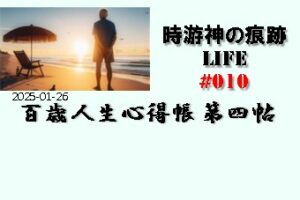あなたのお茶碗の持ち方、それでいい?

日本のマナー 「茶碗の持ち方」 FREE #003
目 次
はじめに
いやはや、びっくりしました。
この人が、こんなことを…。
それは、昨年に我が国の首相に選ばれた石破さんの数々の破天荒とも言えるエピソードです。
いくら近年凋落したとは言え、まだまだ国際的に活躍する日本の、その代表である首相が国際舞台で奇行?とは。
これには日本の将来に大いなる不安を感じざるを得ません。
その中で、石破さんの過去における食事スタイルの写真が出回り、不興を買っています。
ご存じですか?
「箸使いがおかしい」、「テーブルに肘をつけて食べるのは✖」、「おにぎりの食べ方が汚すぎる」などなど。
つまり食事のマナーが何から何までなっていないと、国民からのクレームが爆発しています。
四年前とは言え、そのマナー違反の中の一つに「茶碗の持ち方」があり、これに大いなる危惧を抱きました。
今回はこのお茶碗の持ち方に注目します。
1.クイズです。どこがおかしいでしょうか?
次の画像を見比べてください。



どうですか?
三者三様でいろいろありますが、一番の問題点!
答えはお茶碗の持ち方の良し悪しですね。
この日本の首相お三方のお茶碗の持ち方で、誰が問題でしょうか?
そうです、石破さんです。
このお茶碗の持ち方を「猫がけ」と言います。
正直、我が国の食事ではもっとも下品とされるお茶碗の持ち方なんです。
ところが、結構この持ち方で食事をする人が世間では多いのにびっくりします。
子どもから中高生、ビジネスマン、そして年配の方まで幅広くこの持ち方で食事をしています。
「昔からの癖だよ」と言われるのなら、確かにそうですね。
「持ちやすい」と言う人もいるでしょう。
でも我が国日本における食事マナーとしては最悪の部類に属します。
2.正しいお茶碗の持ち方とは?
もちろん正しい持ち方のルールはあります。
「お作法でしょう? なんか面倒臭い!」
でもね、海外の他の国に行っても、必ずその国独自の食事マナーは存在します。
と言ってもヨーロッパの食事マナーが確立したのは19世紀。
インドや中国、そしてアメリカでもその国、辿った文化、民族、宗教観などが作用して食事マナーが確立しています。
話は逸れましたが、我が国のお茶碗の持ち方は、次の三原則が基本となります。

① お茶碗を右手で持ち上げる。
② 左手の親指以外の4指を揃えて高台(こうだい)を下から支える。
➂ 左手の親指をお茶碗の縁にそえて支える。
この基本マナーについては、小林食品さんのHP
『和食の旨み』
「親指や人差し指の位置は?今さら他人に聞けないお茶碗の持ち方を解説」
に詳しく解説されており信頼性の高い記事ですので、そのエッセンスを以下に紹介させていただききます。
① お茶碗を右手に持ち上げる

右手を使い親指は縁(ふち)に軽くそえて、残りの4本の指で横から胴(どう)を支えて持ち上げる。
お茶碗を持ち上げる際に、上からわしづかみにしたり、親指がお茶碗の内側に入ったりしないように注意する。
またお茶碗が離れた場所に置いてある場合は、手で引きずらずに持ち上げてから自分の元に寄せるようにする。
② 左手の人差し指から小指を揃えて高台を下から支える

お茶碗の底には高台(こうだい)あるいは糸底(いとぞこ)と呼ばれる、円形状に突き出ている部分があります。
右手でお茶碗を持ち上げたら、左手の手の平を上に向けて、親指以外の4本の指の隙間を開けずに揃える。

左手の指を揃えたら、先ほど右手で持ち上げたお茶碗を左手の上に持っていき、左の4本指の上に高台を載せて両手でお茶碗を支える。
この時お茶碗を左手の手の平の上に載せてはいけない。
➂ 左手親指をお茶碗の縁にそえて支える

お茶碗の高台を4本指で下から支えるのと同時に左手の親指をお茶碗の縁にそえる。
この時親指をお茶碗の縁に引っ掛けて内側に入らないようにする。
親指で縁を持ち、高台を残りの4本の指で支えれば上と下からお茶碗が支えられて安定する。

この形が正しいお茶碗の持ち方!
親指を縁に添えて、高台を残り4指を揃えて支えるのが正しい持ち方となる。
いかがですか?
綺麗でしょう? この所作。この形!
これはお味噌汁やお吸い物の、いわゆる椀物も同様ですし、丼ぶりものや小皿も同じマナーです。
3.どうして「猫がけ」になったのか?
これはあくまでも私見ですが、二つのルーツがあるようです。
3-1. 韓国式から広まった?
韓国にも古くから食事マナーはあります。
12の代表的なマナーがあり、その一つに
「器や茶碗を持ち上げてはいけない」というルールがあります。
食器と箸は銀製が基本。
テーブルに置かれた状態で食事が進みます。
これは西洋の食事方式と基本的に同じですね。
銀製などの食器は日本の陶器のように底部に高台がありません。
したがって日本式の碗を持つ文化ではないのです。
唯一、韓国のマッコリなどお酒を飲む際に「猫がけ」になるようです。

これが一般化するとこうなります。

日韓合作の映画シーンでも両者の違いが分かるシーンがあります。

画面左が日本の女優さんで、右側が韓国の女優さん。
両国の違いが歴然としていますね。
茶碗を持って食べる日本のマナーが韓国ではタブーなのです。
その国独自の文化ですから、致し方ありません。
だからこそ互いに認め尊重しつつ、自国の文化を守る必要があります。
3-2. 学校給食から広まった?
学校給食にはいろいろ懐かしい思い出がありますが、我が国での給食の始まりは、明治22年(1889年)に遡ります。
以来、今日に至るまで小学校に止まらず、保育園、幼稚園、中学校にも行き渡っています。
戦後に絞って話をしますが、敗戦で何もない日本に給食が一般化し、全国に普及したのは昭和29年(1954年)に「学校給食法」の成立後でしょう。
当時の食器はアルマイト製で、コッペパンとおかずが丸いお皿に、脱脂粉乳のミルクがお椀でした。

(https://bushoojapan.com/jphistory/kingendai/2019/12/24/65971)
その後、様々な経緯で、食器はプラスティック製に置き換わっていきました。
ただ両者に共通するのは、お椀には高台などなく、底はフラットでした。
これは食器製作におけるコストダウンと大量生産の結果であり、また給食厨房での清潔な洗浄と時間の短縮に役立ったと思います。
しかし、底がフラットだと、中に入っている具材により、熱がそのまま持ち手の指に伝わリます。
子どもの繊細な指には耐えられない熱さです。
熱い脱脂粉乳もそうでしたし、だいぶ後のパン食からご飯食への転換により炊き立てのご飯や温かいスープなどに対しては、椀の側面を5本の指で支えるか、「猫がけ」せざるを得ない持ち方になるでしょう。
これに加えて家庭ではどうだったか?
茶碗の持ち方は昔から箸の扱いと同様に親の躾(しつけ)により、幼児から厳しく矯正されました。
ところが家庭では食事の洋食化が進み、また核家族化で三世代同居が崩れ、さらに夫婦の共稼ぎが一般化すると食事マナーの伝承が希薄になって、躾や教えること自体もおざなりになっていきます。
給食では主にスプーンを用いますから、箸の扱いも含めて、マナーに反した食べ方が常習化して身に付いてしまった癖はもはや治らない状態になります。
如何でしょう?
理由や原因となる歴史はともかく、正しいマナーはその国の生活文化です。
皆さんは「猫がけ」で日々の食事をしていませんよね。
3-3. 昔はどうだった?
前の項では給食の歴史に触れましたが、お椀の持ち方に関する歴史はどうでしょうか?
実は鎌倉時代の食事マナーでは、ご飯を盛ったお椀を持つ事は許されなかったそうです。
床上の膳に置かれたお椀から箸ですくって食べたと言うのです。
これが室町時代に移ると、椀を手に持つようになったようです。
革新的な食事作法の改良です。
この時代に細かな日本的食事作法が定められ、現代にも受け継がれていきました。
江戸時代では下図のような食事風景で椀の持ち方が現代とほとんど同様であることがわかります。

江戸中期のこの絵は、歌川広重の浮世絵「木曽海道六十九次 下諏訪之図」です。
さらに時代が下がり、幕末期に写された写真でも現代のお茶碗の持ち方が分かります。

左の女性の椀の持ち方は、汁物を注ぐときの、手のひらに載せるスタイルで、これは食べる際ではないのでOKですね。
現在の作法の源流は室町時代からおよそ600年の時を歩んでいるわけです。
ただし一部の社会で「猫がけ」せざるを得ない特例がありました。
ちょっと昔の防衛大学校の食事では、アルマイト製と思われる茶碗ひとつひとつにコメと水を入れ、それを一度に大量に蒸かして食事を提供していたため、器が熱く、親指、人差し指、中指で挟むようにしないと持てなかったようです。
ちなみに中国の食事マナーは韓国とほぼ同様ですが、それは周代(紀元前1046年頃 - 紀元前256年)に遡りますからとんでもない歴史です。
それゆえ「茶碗」の意味が違い、字句通りお茶を注ぎ、飲む道具が「茶碗」で、これは手に取ってもOK。
しかし、ご飯類、例えばチャーハンなどは皿に取り、それをレンゲやスプーンで食べます。
皿を手に取り、持ち上げてはいけません。
ヨーロッパの食事マナーも上記とほとんど同様の方式で、手に取って持ち上げて良いのはコップかグラスのみ。
日本はその意味で異端児で、外国人はさぞやびっくりすることでしょう。
4.治せるのなら治しましょう
4-1. 食事マナーは社会人、国際人としての素養
その昔、ある大手企業のお客様と会食の機会を得ました。
若手でとても有能な方でしたが、彼の椀類の持ち方が「猫がけ」でした。
確かに当時は異様に見えました。
後日、その客先では当の若手が人事異動でいなくなりました。
理由は「猫がけ」で、人前での食事作法がまずいと人生を狂わすこともあります。
作法やマナーは国際交流でも重要なキーワードです。
自国の様々なマナーはもちろん、海外に旅行や仕事で行くのならその国のマナーも会得すべきです。
外交活動を担う政府高官や王族ともなれば、国際的行事のルールやマナーは「プロトコール」と言い、きわめて重要なものです。
それは相手方の文化・宗教・風習を尊重することであり、立場が変われば自身の背景でもある自国の文化・宗教・風習を守り、理解し合うことでもあります。
4-2. 教育そのものが問われている
前述の「自国の文化・宗教・風習を守る」にはどうすべきでしょうか?
答えは簡単です。
「教え育てること」、つまり教育しかありません。
ところが今の日本はどうでしょうか?
文科省も、学校も、教師も、熱意を持って躾やマナー教育を推進しているようには到底思えません。
それは家庭や家族の仕事でしょうか?
もちろん親からの躾は大事。でも何も知らない。
いったい誰が真剣に作法、マナーやプロトコルを躾けるのでしょうか?
道徳的な教育はなぜか戦前の軍隊や軍部などを想起し、頭から拒否されます。
それほど戦前の世界が残した負の遺産が大きかった証左でもあるのでしょう。
「自由」な社会は必要ですが、何も枠組みの無い社会は、いつか無法地帯になります。
教育システムのほころびに止まらず、教育そのものが傾き出しています。
古今東西、自国の文化を伝承しない民は必ず滅びる運命にあります。
偏った愛国ではなく、自国の歴史を学びつつ、国際社会に貢献できる人材を育てるための確固たる指針とテキストを示すべきです。
そのためにも石破さん、行儀作法をもう一度、無心に学び直してください。お願いします!
まとめ
ところで当の石破さん、良いとこのお坊ちゃんなんですよ。
父ちゃんは昔、鳥取県知事を務めているし、かあちゃんは国語教師で、教育熱心だったんだって。
石破家の長男坊で、上に二人の姉ちゃんがいて、本人は慶応大学出て、三井銀行にも勤めていたエリートです。
不思議ですね。
家柄、貴賤、出自に関係なく、67歳の現在でも外交マナーや食事マナーが身に付かないなんて。
ある意味、立派です。
が、これらのことが世界に、国際的に、ジャパニーズ・スタンダードと思われたら大変なことです。
生活様式は多様でも、どの国や地域にもマナーやルールは古い時代から受け継がれ、洗練されて今日に伝承されているはずです。
一国の総理が、その足元の自国の食文化の基本すら会得していなくて、どうして国を治め、外交ができるのか?
もちろんこれには賛否両論、是か非か、百花繚乱。
皆様のご意見を賜りたい、ものです。
ただ作法やマナーから外れているなら、これは自分自身で治していかなくてはなりません。
「猫がけ」だけでなく、「犬食い」や「招き舌」、はたまた「くちゃくちゃ食べ」など、周りが嫌がる食事癖は早く気づき、是正しましょう。
ところで「発酵美食」の久保香菜子さんのHP『和食の楽しみ方入門』の、

ここでのお茶碗の持ち方(画像右4)は、茶道での茶碗の持ち方なら良いと思いますが、ご飯茶碗では美しい持ち方には見えません。
どうなんでしょうか?
次回は、続けて石破さんの「箸使い」から歴史と世界についてでもお話ししましょう。
了
皆戸 柴三郎