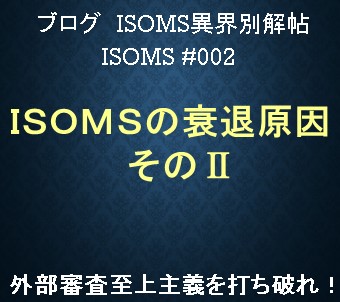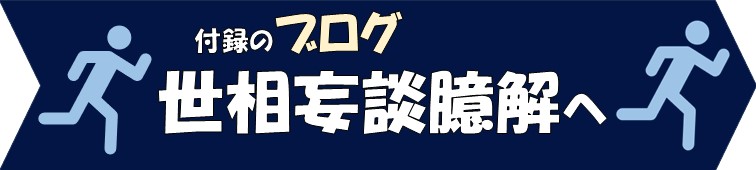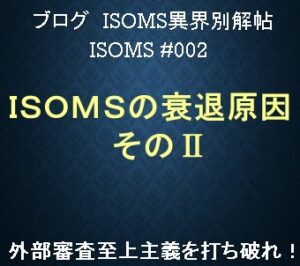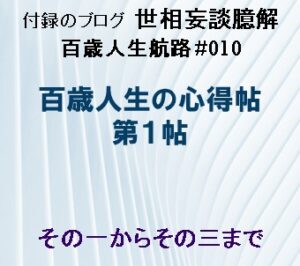このままで良いはずがない ISOMS

ISOMSの衰退原因 そのⅠ ISOMS#001
ここではISOMS(QMS、EMS)の衰退原因を4回にわたり、解説します。
衰退原因を知ることで、今後のISOMS維持に有用なヒントが必ず生まれてきます。
目 次
はじめに
ISOMS 9001が爆発的に世間の注目を集めたのは1994年のことでした。
そこから約30年の歳月が経過しました。
現在、日本でのJAB認定件数の推移を見ると、品質マネジメントシステム(ISO 9001)は2006年頃、環境マネジメントシステム(ISO 14001)は2010年頃をピークに、それぞれ下降の一途をたどっています。

およそ4割強の組織がISOMS認証を返上してしまったのです。
もちろん認証返上の理由は組織ごとに様々でしょう。
しかし、このまま衰退が続いてよいのでしょうか。
ISOマネジメントシステム(以下、ISOMS)は、組織運営のエッセンスが巧みに組み合わされたものです。
それを生かして生産性や経済性を高めなければ、認証取得や維持の意味はありません。
本ブログは、「これでいいのか?このままで大丈夫か?」というシンプルな疑問から始めます。
昨今のISOMS衰退に繋がっている不可解なシステム運用全体を、やや斜めの視点で観察しながら、こうしたほうが良いのではないかと提言していこうと考えています。
もしかしたらここからISOMS再生の道が見えてくるかもしれません。
1. ISOMS認証返上の主な理由
調査や聞き取りを通じて、ISOMS認証を返上した組織が口にする理由は大きく5つに集約されます。
- 文書・記録作成の手間と負担の増大
- 業務そのものの負担増
- 当初期待していた効果の失墜
- ISOMS審査対応の不備
- 高額な審査費用および維持費用
これらはいずれも、結果的に経営面および経済面での投資対効果が期待通りでなかったことを反映しています。
中には「ISOMSが定着したため」や「外部からの要求がなくなった」という理由での返上もあります。
しかし、これらのいろいろな返上理由の背景には、もっと深い組織的な事情が隠されているはずです。
例えば、ISOMS導入で業務が増えたという点は、文書作成や業務負担の増加(理由1・2)に現れています。
審査対応の不備(理由4)は、審査機関との関係性だけでなく、組織側の審査に対する取り組み姿勢に由来します。
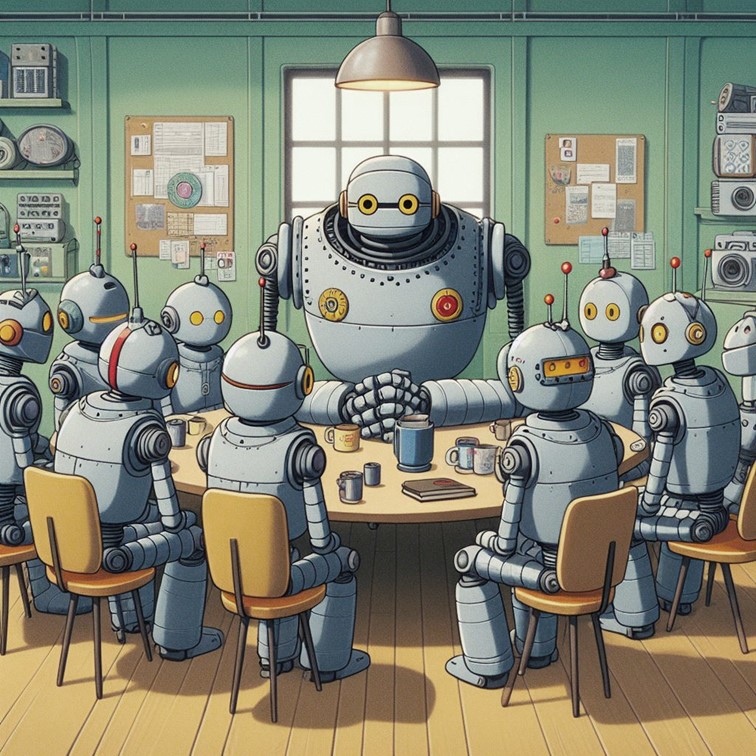
2. ISOMS認証返上の原因は?
返上理由の背後には、次の4つの組織的原因があると考えられます。
- 古い組織体質のまま、ISOMSの改革が進んでいない
- 外部審査を組織の重要な中核イベントにしてしまっている
- ISOMS維持部門が組織内で権威的・閉塞的になっている
- 組織トップがISOMS自体に興味を持たない
この4つの原因が複合的に作用し、認証返上に繋がっています。
それでは、原因aから掘り下げてみましょう。
3. 原因a:古い組織体質のまま、ISOMSの改革がない
ISOMSマネジメントシステムが世界標準として整備されてから30年余り。
初期は認証取得組織も審査機関も皆が初心者同然でした。
その中で、ISO 9001と14001が品質・環境の両輪として普及しました。
しかし、当初から次の3つの問題が現れていました。
ⅰ. 規格にどこまでも忠実な解釈
ⅱ. 画一的な表現の品質及び環境マニュアル
ⅲ. 膨大な文書と記録様式の作成及び保管
特に「規格に忠実すぎる」ことは問題です。
ISOMS規格は原文が英語であり、その翻訳・JIS化には誤訳や曖昧さも含まれます。
結果的には、日本の多くの組織は規格要求に忠実に従い、重厚長大なシステムを構築してきました。
また、審査員によって解釈の幅や厳密さが異なるため、現場は混乱しがちです。
一方、マニュアル類は「ISOMS規格の要求事項に順応した文言」をそのまま並べた画一的なものが多く、外部審査には便利でも、現場の実態に即して使われているとは言い難い状況です。
近年は「プロセス・アプローチ審査」が主流になり、規格表現に縛られる必要は減りましたが、古い体質のままのマニュアルを引き継ぐ組織はいまだ多く存在します。
さらに、膨大な文書・記録の作成・保管は大きな負担であり、多くの組織でISOMS用の業務が「本業」と切り離され、ISOMS対応用の仕事として分離・固定化しています。
これによりISOMS活動が組織全体の一体的な運営から乖離し、負担感が増大しているのです。
こうした古い体質が残ることで、経済効果が見えずモチベーションが低下し、認証返上の道を辿っているのが現状なのです。
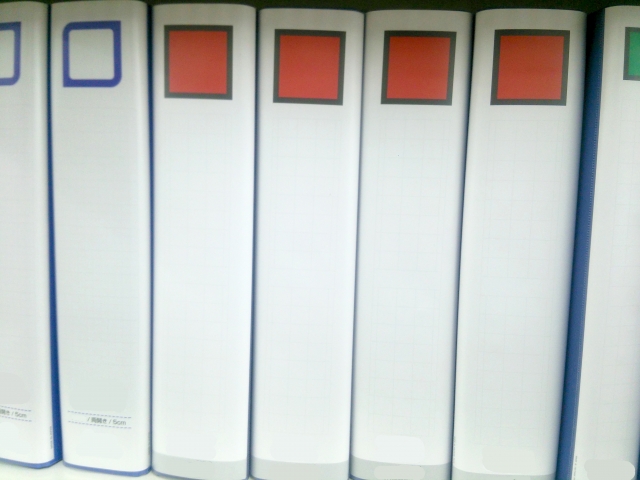
今回は、ISOMS衰退原因のⅠとして、一つ目の原因「古い体質のまま改革なし」を考察しました。
次回は、二つ目の原因「外部審査のイベント化」について考えていきます。
了
By イソ丸研究所
※本記事は2023年12月に執筆掲載したものですが、今回のブログ改装で再編集しました。