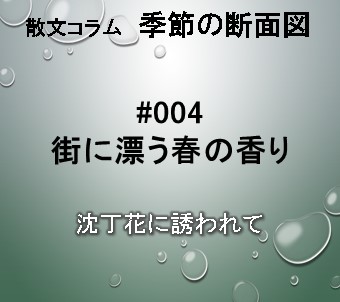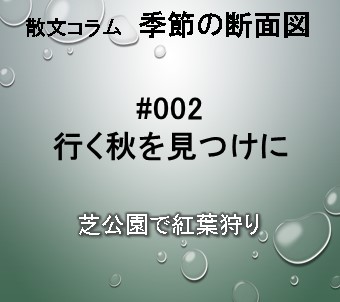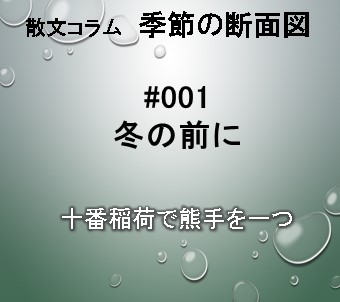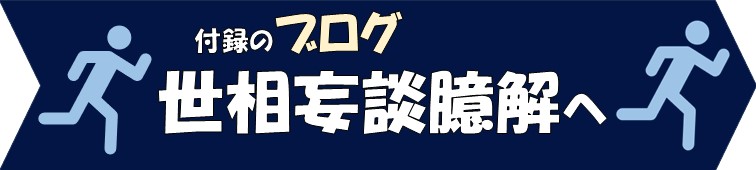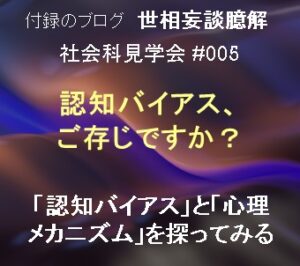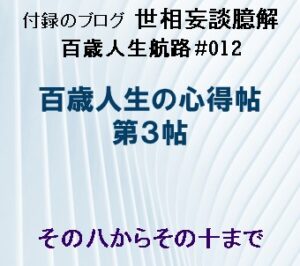梅まつりに出掛けた
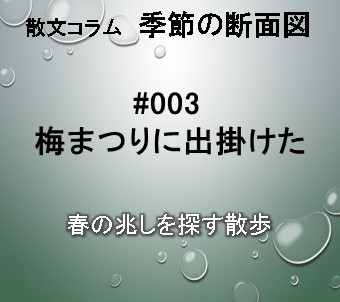
春の兆しを探す散歩 季節の断面図 #003
目 次
⋄ プロローグ
立春を過ぎても、まだ冬の名残は街のあちらこちらに居座っている。
だが、陽射しの奥にわずかなぬくもりを感じると、心はそわそわし始める。
そんなある日、芝公園で「梅まつり」の看板を見つけ、小さな春探しに向かった。

⋄ 取りこぼした季節のカケラ
大晦日、正月、節分……
例年ならブログに書き残すはずの風物詩を、今年はことごとく取り逃がした。
「老化のせいかもしれぬ」などと冗談めかしつつ、日々は駆け足で過ぎていく。
気づけば二月半ば。
春の前触れを告げるのは、梅の花だ。
白と紅の小さな花が、冷たい空気にほのかな香りを放つ季節である。
⋄ 公園の小さな梅林
この公園にある梅林は、驚くほどその規模が小さい。

公式には七十本、実際には老木も多く六十数本。
紅梅、白梅、黄梅……九種類の梅が、冬の名残を振り払い、枝先に花を灯している。



この「梅まつり」は一日だけ。
かつては野点の茶席もあり、和服姿の茶人が華を添えていたが、今年はそれもない。
代わりに、管理チームの方々が小さなテントを張り、訪れる人々を静かに迎えていた。
園内には「銀世界」という案内板がある。
梅林の名前だ。
白梅の咲き乱れる光景を連想するが、
実際は江戸時代の梅屋敷「銀世界」の名を受け継いだものらしい。
歴史の余韻が、小さな看板に宿っている。
⋄ 「梅に鶯」は本当か?
梅といえば「梅に鶯」。
ただ、都会で本当にその光景に出会うことがあるだろうか?
私はその日、初めて目にした。
梅の枝に止まる小さな鳥。

蜜を吸っている姿が愛らしい。
だが、待てよ?
それは鶯ではなく、たぶんメジロだ。
それでもいい。
梅の花と緑の小鳥。
この取り合わせだけで、春の情緒は十分に満ちていた。
⋄ 観梅という文化
梅を愛でる習慣は、奈良・平安の宮廷に始まる。
唐から渡った梅は、当時の貴族にとって高級な舶来品だった。
やがて江戸の町人文化に下り、現代の「梅まつり」へと続いている。
関東には、偕楽園や湯島天神、曽我梅林などの名所がいくつもある。
だが、私はあえて、この小さな庭園に足を運ぶ。
華やかさはないが、都会の片隅で見つける春は、なぜこうも心に沁みるのだろう。
⋄ エピローグ
万葉の時代から詠まれた梅。
春を告げるその花を、私たちは千年の時を越えて、同じように見上げている。
『春されば まづ咲くやどの梅の花ひとり見つつや 春日暮らさむ』
(山上憶良)
庭先の梅を一人見ながら過ごす春の一日
──その感覚は、現代にも変わらず息づいている。
私もまた、同じ時間をこの梅林で生きている。

⋄ 梅祭りの名所
《関東》
- 偕楽園(茨城県):2025年2月11日(火・祝)~3月20日(木・祝)
- 坂田城跡梅林(千葉県):2025年2月22日(土)~3月9日(日)
- 観音山梅の里梅園(栃木県):2025年3月9日(日)~16日(日)
- 榛名梅林(群馬県):2025年3月中旬~2025年3月下旬
- 曽我梅林(神奈川県):2025年2月1日(土)~2月24日(月・祝)
- 越生梅林(埼玉県):2025年2月15日(土)~3月16日(日)
《東京》
- 湯島天神:2025年2月8日(土)〜3月9日(日)
- 高尾梅郷:2025年3月8日(土)・9日(日)

了
By 皆戸 柴三郎
※本記事は2025年2月に掲載したものですが、今回ブログの全面改装で再編集、再掲載しました。