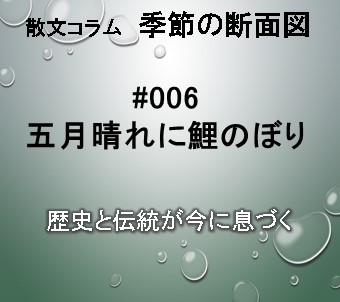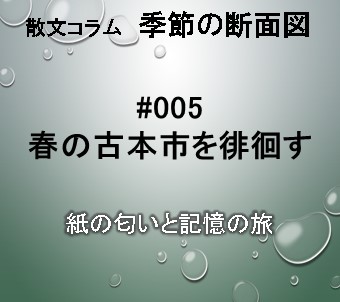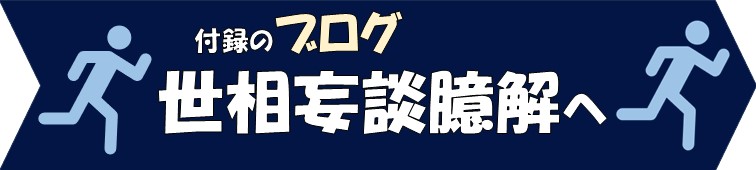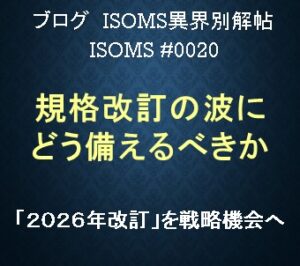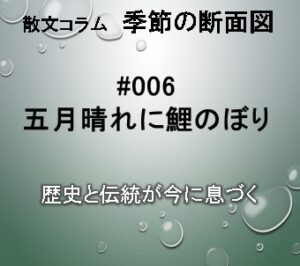ほおずき市だよ
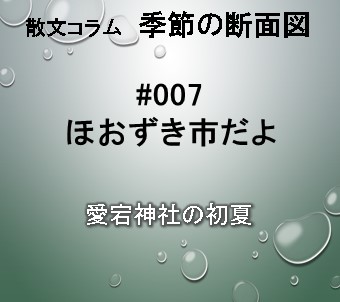
愛宕神社の初夏 季節の断面図 #008
目 次
⋄ プロローグ
初夏の東京、愛宕山の頂に鎮座する愛宕神社では、
鮮やかなオレンジ色のほおずきが揺れる「ほおずき市」が開かれる。

江戸時代から続くこの市は、都会の喧騒の中にあっても、
日本の庶民文化の奥深さと時の流れを伝える貴重な風物詩だ。
石段を登りきると、都心とは思えない清々しい境内が広がり、
整備された池には鯉がゆったり泳ぐ。
⋄ 江戸の名所「出世の石段」
愛宕山の「出世の石段」は、
三代将軍家光に梅を献上した曲垣平九郎の故事に由来する。
急勾配の石段を馬で駆け上がったという逸話は、
歴史と個人の願いが結びつく象徴的な道程として、
今も登る人々の心を刺激する。



石段を踏みしめながら見上げる空には、夏を告げる茅の輪が設置され、
左右に八の字を描くようにくぐる「夏越の祓」の儀式が行われる。
これにより半年間の穢れを祓い、無病息災を願う古来の信仰が、
現代の都市生活者にも生き生きと伝わる。

⋄「ほおずき市」の歴史と文化
「ほおずき市」の彩りは、五感を通じて初夏を印象づける。
まだ青い実は「これからの色変わり」を予感させ、
赤く染まったほおずきは、提灯のように柔らかな光を思わせる。

参拝者が手に取るたび、自然の変化と人々の営み、文化の歴史が結びつく。
青い実から赤への移ろいは、
初夏から朱夏へと変わる季節の息吹であり、豊穣や希望の象徴でもある。
市には、多くの人々が行き交い、屋台や鉢植えのほおずきの間を歩く。
その声や笑い声、風に揺れる葉音が境内に響き、都市の雑踏を忘れさせる。
江戸の昔から続く「千日詣」の功徳日には、
参拝するだけで千日分のご利益があるとされる伝統が息づき、
現代の私たちもまた、歴史の一端に触れる感覚を味わうことができる。


愛宕神社のほおずき市は、単なる季節の行事ではない。
急な石段、茅の輪、青々とした鉢植え、賑わう参拝者たち。
これらが交錯することで、
初夏の景色は五感に刻まれ、文化的な体験として心に残る。
変化を受け入れ、自然のサイクルに身を委ねる喜びが、ここにはある。
ほおずきの赤い光が夏の夜をほのかに照らすように、
私たちも季節の移ろいの中で、
新たな発見や喜びを手にすることができるのだ。
⋄ エピローグ
江戸から令和へと受け継がれる伝統行事は、
時代に合わせて形を変えつつ、その本質を失わずに息づいている。
ほおずき市は、都会の中の自然と歴史、人々の営みが交わる場所として、
心を豊かにする時間を与えてくれる。
足元から見上げるほおずきの彩りは、今年の夏を記憶に刻む小さな旅の証となってくれるのだ。


関東地方の主なほおずき市紹介
(詳しくは、それぞれのリンク先でご確認ください)
・愛宕神社 (港区) | 6月23日・24日 | 発祥の地 | 千日詣り
・浅草寺 (台東区) | 7月9日・10日 | 四万六千日
・龍泉寺 (茨城県龍ヶ崎市) | 7月10日 | 龍ケ崎観音がある | 四万六千日
・出雲大社相模分祠 (神奈川県秦野市) | 7月12日・13日 | 夏詣の一環
・源覚寺 (文京区) | 7月19日・20日 | こんにゃく閻魔で有名
了
By 皆戸 柴三郎
※本記事は2025年6月に掲載したものですが、今回ブログの全面改装で再編集、再掲載しました。